失敗しないクリニック開業物件選定
物件選定 ~現地確認 ~テナント編~~


医療設計のコーディネーターをしています鈴木です。
物件選定の際の最重要事項の一つである現地確認。
今回は、テナント編です。
今回は、テナント編です。
現地確認を行うことで、次のことが解るようになります。

戸建て編の時と重複致しますが
図面や地図、ストリートビューなどでは解らないことが現地に行くと見えてきます。
また、出来るだけ現地見学の際は、先輩ドクターや医療実績のある方の同席を依頼して下さい。
他の人や専門家の意見は重要な参考となります。
図面や地図、ストリートビューなどでは解らないことが現地に行くと見えてきます。
また、出来るだけ現地見学の際は、先輩ドクターや医療実績のある方の同席を依頼して下さい。
他の人や専門家の意見は重要な参考となります。
それでは、テナントの現地確認を行う際の大きなポイントをご紹介させて頂きます。

★現況と図面の相違点
ここで言う図面とは、
ここで言う図面とは、
不動産屋さんが公開している簡単な図面ではなく、建物が竣工した時の図面=竣工図面となります。
建物オーナーや管理会社が所有していますので、確認することが大切です。
建物オーナーや管理会社が所有していますので、確認することが大切です。
特に、建築年数が経過している物件は注意が必要です。
テナントが何度も入れ替わったことにより、竣工図面と現況が異なっている場合があります。
テナントが何度も入れ替わったことにより、竣工図面と現況が異なっている場合があります。
実際に私が現地確認を行い、経験したことを記載させて頂きます。
・排水管が無くなっている
・窓の大きさが変わっている
・入口の場所が異なっている
・電気容量が少なくなっている
・区画の壁位置が異なっている
・柱の大きさや位置が違う などなど
・排水管が無くなっている
・窓の大きさが変わっている
・入口の場所が異なっている
・電気容量が少なくなっている
・区画の壁位置が異なっている
・柱の大きさや位置が違う などなど
レイアウトに影響する場合がありますので、早い段階で現況と図面の相違を確認する方が良いです。

★防火対象物の用途区分
消防用途とも言われています。
建物には、必ず防火対象物の用途区分が決まっています。
理由として、管轄の消防署が有事が起こった際に
どのような建物なのか?
どういう人がいるのか?
を判断するためです。
消防用途とも言われています。
建物には、必ず防火対象物の用途区分が決まっています。
理由として、管轄の消防署が有事が起こった際に
どのような建物なのか?
どういう人がいるのか?
を判断するためです。
下記の表のように、大きく20の項目に分かれています。

※総務省消防庁のHPより引用
なぜ注意が必要なのか?
クリニックは飲食店などと同じで、不特定多数の人が来る施設とされているためです。
テナントで比較的多い事務所や学習塾などは、特定の人が来る施設とされています。
特定の人が来る施設で構成している建物は、
「特定者」と言うことで、防災設備の設置基準が低いです。
このような建物に、クリニックが入居することにより、「特定者」から「不特定多数」の人が利用する建物に変更する場合があります。
この場合、用途区分が変更となり、建物全体の防火設備の設置基準を上げる必要がある場合があります。
そのため、上がった設置基準の防災設備を順守する必要があるのです。
このような建物に、クリニックが入居することにより、「特定者」から「不特定多数」の人が利用する建物に変更する場合があります。
この場合、用途区分が変更となり、建物全体の防火設備の設置基準を上げる必要がある場合があります。
そのため、上がった設置基準の防災設備を順守する必要があるのです。
設置基準に満たしていない場合、
満たすための防災設備の追加工事を行う必要があり、工事費用が発生致します。
ここで、この工事費用を誰が負担するのか?
と言う問題が出てきます。
と言う問題が出てきます。
クリニックが入居することによる変更のためクリニック側?
建物資産として残るため建物オーナー側?
建物の規模にもよりますが、数十万~数百万、数千万となる場合があります。
上記により、建物オーナーから入居不可と言われることもあります。
このため、用途変更が発生する場合、注意が必要となります。
上記により、建物オーナーから入居不可と言われることもあります。
このため、用途変更が発生する場合、注意が必要となります。
特に、賃貸借契約を締結した後に発覚した場合、大問題となる場合もあります。
注意して頂きたいポイントとして、事務所だけのビルや事務所や塾など特定者利用がほとんどのビルとなります。
用途変更に関しましては、建物オーナーや不動産仲介会社など把握していないことがほとんどです。
そのため、医療施設を経験したことのある専門家に事前に相談することをお勧め致します。
そのため、医療施設を経験したことのある専門家に事前に相談することをお勧め致します。

★電気容量の確認
区画内にブレーカーがあることがほとんどのため、まずはブレーカーを確認して下さい。
テナントの電気は、電灯と動力の2種類あり、それぞれの容量を確認することが大切です。
区画内にブレーカーがあることがほとんどのため、まずはブレーカーを確認して下さい。
テナントの電気は、電灯と動力の2種類あり、それぞれの容量を確認することが大切です。
電気容量が足りない場合
先生が導入したい医療機器などが設置できない場合がありますので、注意が必要です。
電気容量が不足の場合
増やすことが出来るのか?
また、増やす方法はどのように行うのか?
建物を管理している管理会社や専門家、電気業者へ相談や確認が必要となります。
増やすことが出来るのか?
また、増やす方法はどのように行うのか?
建物を管理している管理会社や専門家、電気業者へ相談や確認が必要となります。
電気容量を確認するにあたり、
先生が開業して使用する医療機器(開業時だけでなく将来導入含む)を確認する必要があります。
そのため、何の医療機器を導入するのか?
なるべく早い段階で方向性を決めて頂く方が良いです。
先生が開業して使用する医療機器(開業時だけでなく将来導入含む)を確認する必要があります。
そのため、何の医療機器を導入するのか?
なるべく早い段階で方向性を決めて頂く方が良いです。

簡単ですが、電気容量を必要とされている物を記載させて頂きます。
・CT、X線
・MRI
・オートクレーブ
・超音波
・レーザー(皮膚科)
・CT、X線
・MRI
・オートクレーブ
・超音波
・レーザー(皮膚科)
医療機器では無いですが
・電子レンジ
・暖房機器(ドライヤーや足元用のヒーターなど)
★工事区分の確認
建物により、一部の工事に関して工事会社が決まっている場合があります。
理由として、工事区分が決まっているためです。
比較的大きい建物の場合、下記のように工事区分が分かれていることがあります。
建物により、一部の工事に関して工事会社が決まっている場合があります。
理由として、工事区分が決まっているためです。
比較的大きい建物の場合、下記のように工事区分が分かれていることがあります。

B工事の有無を確認することが大切です。
B工事が無い建物もありますので、物件選定時は工事区分の有無について確認をして下さい。
B工事が無い建物もありますので、物件選定時は工事区分の有無について確認をして下さい。
B工事は工事金額の際に重要となるため、改めて記事にてご紹介させて頂きます。
★仲介会社(不動産会社)
テナント選定する際に、仲介会社は必ずと言っていいほど必要となります。
しかし、仲介会社の多くは、ここで紹介した上記のことを知らない人がほとんどです。
知らないのに賃貸借契約を急かしてくる担当者もいます。
賃貸借契約後に上記のことが解り、
余計な費用を負担しなければならない場合や問題となる場合がありますので、注意が必要です。
テナント選定する際に、仲介会社は必ずと言っていいほど必要となります。
しかし、仲介会社の多くは、ここで紹介した上記のことを知らない人がほとんどです。
知らないのに賃貸借契約を急かしてくる担当者もいます。
賃貸借契約後に上記のことが解り、
余計な費用を負担しなければならない場合や問題となる場合がありますので、注意が必要です。

テナントの現地確認の注意事項は上記以外にもまだまだあります。
そのため、何度も重複しますが、現地見学の際は、先輩ドクターや医療実績のある方の同席を依頼して下さい。
そのため、何度も重複しますが、現地見学の際は、先輩ドクターや医療実績のある方の同席を依頼して下さい。
次回は、希望エリア・ポイントについてご紹介したいと思います。
開業希望情報を登録するだけで、条件に合う物件提案が届きます
1. 待っているだけで物件情報が届く
開業したいが物件を探す時間がない、という先生には、開業希望条件を登録するだけで、条件に合う物件を提案しています。
2. ご相談・ご提案無料
登録いただくと、オンライン相談、クリニックサポート登録企業からの提案などを無料でご利用いただけます。
3. 個人情報は非公開
お名前、メールアドレス等の個人を特定できる情報は企業側に公開されませんので、営業電話の心配もありません。









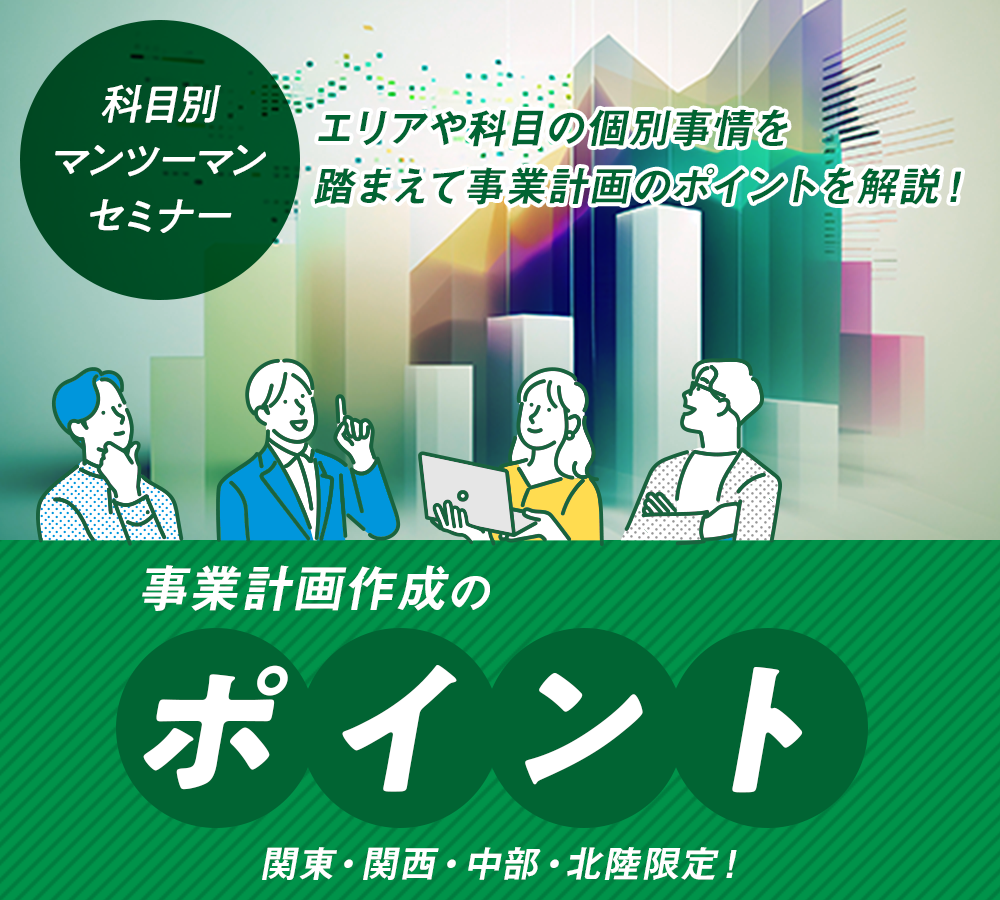
 週間閲覧数ランキング
週間閲覧数ランキング




